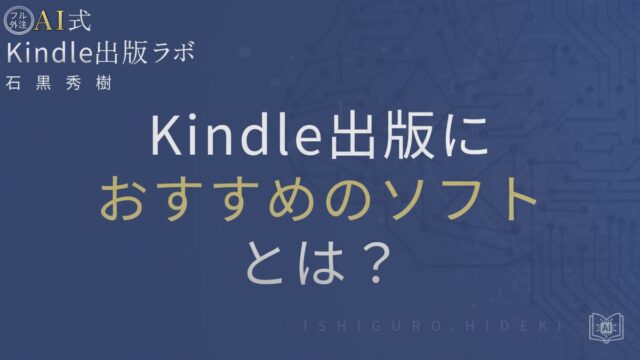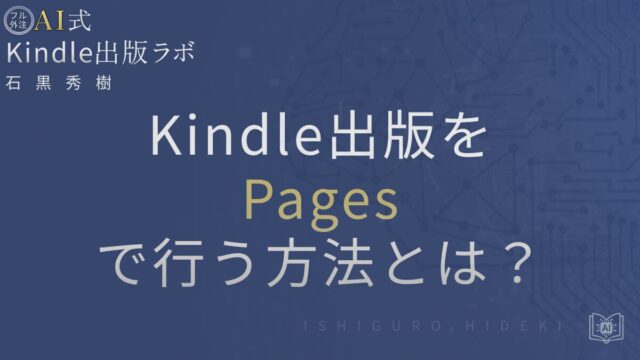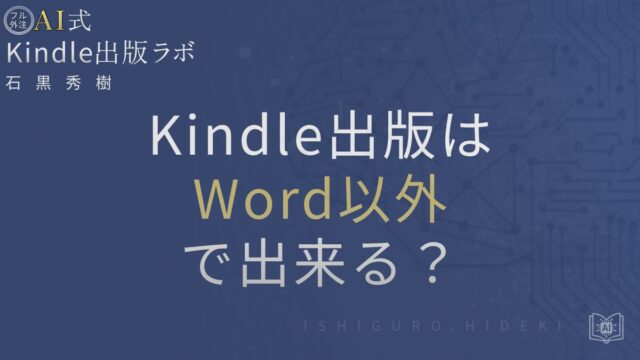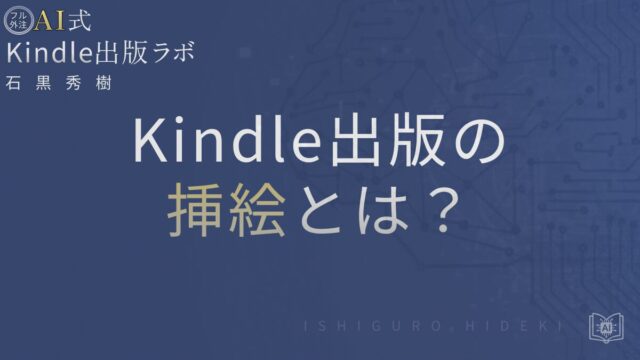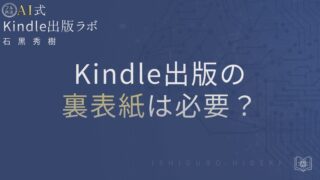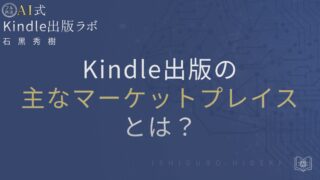Kindle出版の奥付とは?必要項目・作り方・正しい位置を徹底解説
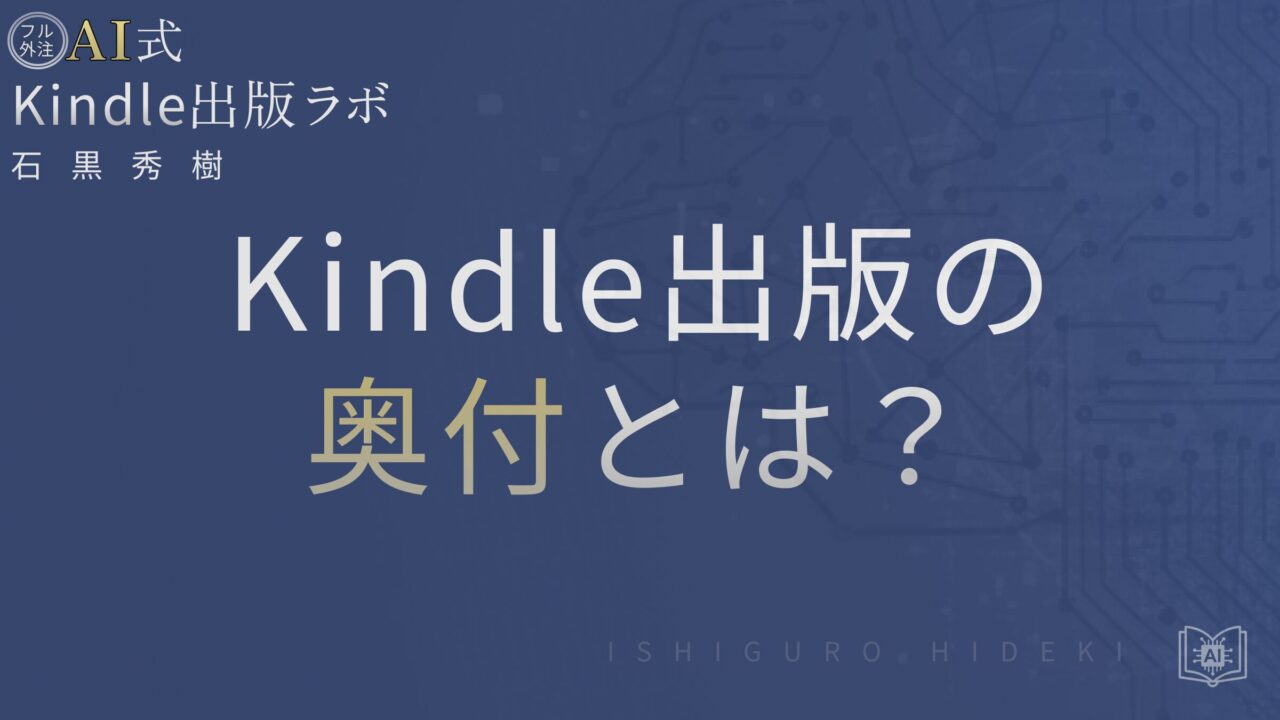
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle本を作っていて、「奥付って入れないといけないの?」と迷う方はとても多いです。
紙の本では当たり前にある奥付ですが、電子書籍では位置づけや必須項目が少し異なります。
この記事では、Kindle出版における奥付の基本的な考え方と、初心者が迷いやすいポイントをわかりやすく整理して解説します。
実際に私自身も、初めてKDPで出版したとき「紙の本と同じように奥付を作らなきゃ」と思い込み、余計な情報を詰め込みすぎてしまった経験があります。
公式ルールを理解しつつ、実務的に最適な形を知っておくことで、ムダな手戻りを防ぎ、見栄えのよい本に仕上げることができます。
🎥 1分でわかる解説動画はこちら
↓この動画では、この記事のテーマを“1分で理解できるように”まとめています。
実際の流れを映像で確認したあと、詳しい手順や注意点は本文で解説しています。
動画では全体の流れを簡単にまとめています。
さらに実践に役立つ情報や具体的な成功事例は、
下のフォームから無料メルマガでお届けしています。
▶ 制作の具体的な進め方を知りたい方はこちらからチェックできます:
制作ノウハウ の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
Kindle出版における「奥付」の基本|電子書籍ではどう扱う?
目次
Kindle出版における「奥付」は、紙の書籍と同じような必須ページではありません。
ですが、著作権や発行日、著者名などを整理して記載しておくことで、読者からの信頼性が高まり、後々の権利トラブルを防ぐ役割も果たします。
ここでは、まず「奥付とは何か」を整理し、そのうえでKindle電子書籍における扱い方を順に解説していきます。
そもそも奥付とは?紙の本との違いを理解しよう
奥付とは、本の巻末に記載される「発行に関する基本情報」のことです。
紙の書籍では、発行日・著者・出版社・印刷所などが明記され、出版物としての信頼性を担保する役割を担っています。
一方、Kindle電子書籍では出版社や印刷所といった概念がなく、データとして配信されるため、紙と同じ体裁をそのまま適用する必要はありません。
ここを混同してしまい、「紙と同じ書式を忠実に再現しよう」として余計な要素を盛り込みすぎるのが、初心者の方によくあるパターンです。
実務的には、奥付はあくまで「書籍情報の整理」であり、シンプルな形式で十分です。
Kindle電子書籍では奥付は「必須」ではない
奥付がなくても出版は可能です。
また、奥付の有無のみを理由に差し戻されるとは限りません(詳細は公式ヘルプ要確認)。
ただし、著作権や発行日の記載がないと、第三者との権利関係で誤解を招いたり、書籍情報として不十分と見なされる可能性があります。
そのため、多くの著者は「巻末1ページに基本情報をまとめておく」形式を採用しています。
紙の本とは違い、法律で細かく定義されているわけではありませんが、読者や第三者から見ても著者情報が明確になっていることは信頼につながります。
KDP公式ルールと日本仕様の位置づけ
KDPの公式ガイドラインでは、日本のKindle電子書籍において奥付に必須項目は設定されていません。
そのため、公式には自由度が高いページといえます。
一方で、日本の出版文化では「奥付ページがある」のが一般的という背景もあり、多くの著者が自主的に奥付を用意しています。
実務的には、著作権表記(©+年+著者名)、著者名、発行日といった基本的な3項目を巻末にまとめておく形が主流です。
海外向けの出版を行う場合は、これに英語の著作権表記を1行加える程度で十分対応可能です。
なお、ペーパーバックでは奥付ページの位置や仕様が電子書籍と異なるため、紙版も出す場合は別途確認が必要です。
ここまでを押さえておけば、「Kindleの奥付って何をどう書けばいいの?」という最初の壁はクリアできます。
詳しい権利関係や著作権ページの作り方は『Kindle出版と著作権の基本|出版前に確認すべき権利と注意点を徹底解説』でまとめています。
Kindle出版で奥付を入れる目的とメリット
Kindle電子書籍では奥付は必須ではありませんが、実務上は多くの著者が「巻末1ページ」に基本情報をまとめています。
その理由は単に「形式だから」ではなく、読者からの信頼性を高め、将来的な権利トラブルを防ぐためです。
ここでは、奥付を入れる2つの大きな目的とメリットについて解説します。
著作権・発行日・著者名を明記することで信頼性を高める
奥付に著作権や発行日、著者名といった基本的な情報を明記することで、本の「正式な情報源」が明確になります。
これは、読者に対して「きちんとした出版物である」という印象を与えるうえで非常に大切です。
特にKindleでは、匿名の著者やペンネームで出版するケースも多く、情報が曖昧だと信頼性が下がってしまうことがあります。
実際、私も最初の出版では奥付を省略していましたが、後から読者から「発行日がわからない」「誰の本かわからない」と問い合わせを受けたことがあります。
それ以降は著作権表記(©+年+著者名)、著者名(ペンネーム可)、発行日の3点をシンプルに入れるようにしたところ、問い合わせがピタッと止まりました。
このように、奥付は見た目以上に「信頼のサイン」として機能します。
また、KDPの公式情報では奥付は任意です。
一方で、権利表示や発行情報の明記は実務上の推奨として広く使われています(公式ヘルプ要確認)。
特別なフォーマットは不要で、最低限の情報を整然と記載するだけで十分です。
この「整然と」が意外と重要で、文字サイズを統一し、レイアウトを崩さずにシンプルにまとめると全体の完成度も上がります。
著作権表記の正しい書き方や注意点は『Kindle出版と著作権の基本|出版前に確認すべき権利と注意点を徹底解説』で詳しく紹介しています。
読者・第三者とのトラブル予防や権利保護にも役立つ
奥付にはもう一つ重要な役割があります。
それは、著作権や発行日の明記が、万一の権利トラブルの際に証拠として機能することです。
Kindleではコンテンツの盗用や無断転載といった問題も珍しくありません。
明確な著作権表記と発行日があるだけでも、「自分が先に出版していた」という証明材料になります。
私の知人の著者の中には、奥付をきちんと残していたことで、他者からの権利主張をスムーズに退けられたケースもあります。
逆に、奥付がなかったために自分の出版日や権利主張を裏付ける資料がなく、対応に時間がかかってしまった人もいました。
このようなリスクを考えると、巻末1ページを用意しておく手間は、将来的な安心につながります。
さらに、読者側から見ても奥付が整っている本は安心感があります。
特に情報商材的な書籍や権利関係が曖昧なジャンルでは、「きちんと著作情報を明記しているか」が信頼の判断材料になることも少なくありません。
その意味でも、奥付は「見えない信用構築ツール」といえるでしょう。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
Kindle電子書籍の奥付に入れるべき基本3項目
Kindle電子書籍では、奥付の形式が法律や規約で細かく決められているわけではありません。
そのため、最初に作るときに迷いやすいポイントでもあります。
とはいえ、最低限の3項目を押さえておけば、見た目も機能も十分な奥付ページが完成します。
ここでは、実際の出版現場でも多くの著者が採用している基本の3項目を順番に解説します。
1. 著作権表記(©+西暦+著者名)
もっとも重要なのが著作権表記です。
「©(コピーライトマーク)+西暦+著者名」というシンプルな形式でOKです。
たとえば、2025年に石黒秀樹という名前で出版するなら、
「©2025 石黒秀樹」
と記載します。
この一行があることで、「この本の著作権は誰にあるか」が明確になります。
KDPの公式ガイドラインでも、著作権表記は必須ではないとされていますが、実務的には権利を明示するために入れておくのが一般的です。
私は過去に奥付を省略していたとき、第三者から「著作権は放棄されているのか」と問い合わせを受けたことがあり、それ以降は必ず著作権表記を入れるようにしています。
ちょっとした一行でも、法的な意味と安心感が全く違ってきます。
2. 著者名・発行者名(ペンネームでもOK)
次に記載すべきは、著者名または発行者名です。
ここは本の責任主体を明示する部分であり、ペンネームを使用している場合でもそのまま記載して問題ありません。
実際、多くの個人著者はペンネームで活動しているため、ここで本名を無理に出す必要はありません。
ただし、法人として出版している場合や複数人で制作している場合は、代表者や発行者名を明記しておくと読者にとってもわかりやすいです。
著者名が明確に記載されていることで、「この本は誰の作品なのか」がひと目で伝わります。
電子書籍では匿名性が高いため、著者名を記載しないと不信感を持たれるケースもあるので注意が必要です。
3. 発行日・初版日(出版日を明記)
3つ目は発行日、あるいは初版日です。
これは「いつ出版された本なのか」を示すもので、読者だけでなく自分自身の管理にも役立ちます。
特に改訂版を出す場合、初版日と改訂日を分けて記載しておくと、更新履歴が整理されて便利です。
たとえば、
「初版:2025年4月1日」
「第2版:2025年10月10日」
のように書くと、後から見たときにすぐ確認できます。
Kindleでは電子的に更新が可能なため、紙の本ほど厳密な版管理は必要ではありませんが、実務的には発行日を入れておくことで自分の履歴が残り、問い合わせ対応などにもスムーズに活用できます。
(補足)海外販売がある場合の英語表記の一行併記
もし日本以外のAmazonストアでも販売する場合は、英語での著作権表記を1行追加しておくと安心です。
たとえば、
「Copyright © 2025 Hideki Ishiguro」
というように、日本語表記の下に英語を添えるだけでOKです。
これは必須ではありませんが、海外ストアでも販売する場合は、
“Copyright © {Year} {Name}” を1行併記すると分かりやすく、問い合わせ対応も円滑です。
逆に、国内販売だけであれば日本語表記だけで十分です。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
Kindle出版での奥付の正しい位置と作成手順
奥付は、ただ内容を書けばよいというものではありません。
本のレイアウト全体において「どこに配置するか」と「どう作るか」がとても重要です。
Kindle電子書籍では、紙の本と違ってページ数や物理的な裏表紙がないため、配置場所や作成方法を間違えると、読者の体験を損なうことがあります。
ここでは、基本の位置と実際の作成手順、そして画像として奥付を挿入する場合の注意点を順番に解説していきます。
奥付は「巻末1ページ」が基本位置
奥付の位置は“本文の完全な後ろ”に改ページで独立化が基本。
目次や本文中に混在させないことが読者体験の面でも推奨です。
紙の本のように裏表紙やカバー袖があるわけではないため、巻末以外に奥付を入れてしまうと、読者が本文と勘違いしたり、読了後に不自然な空白ページが残ることがあります。
特に、目次の直後や本文中に奥付を挿入してしまう初心者の方も多いのですが、これでは本来の役割を果たせません。
私も最初の出版時に、目次の後に奥付を入れてしまい、読者から「本文が急に終わったように感じた」という感想をもらったことがあります。
その経験からも、奥付は必ず「本文がすべて終わったあと」に1ページだけ独立して配置するのが最も自然です。
また、KDPの仕様上、巻末に配置したテキストは目次に自動的に登録されません。
これは裏を返せば、「目次に表示させる必要がない奥付」にとって理想的な位置ともいえます。
WordやGoogleドキュメントで奥付を作る手順
奥付の作成自体は難しくありません。
WordやGoogleドキュメントで作る場合は、以下の流れで進めるとスムーズです。
1.本文の最後に「改ページ」を入れる(改行ではなく、必ず改ページ)
2.新しいページに、奥付の3項目(著作権・著者名・発行日)を記載する
3.テキストは中央揃え、フォントサイズは本文と揃えるか、やや小さめでOK
4.余白を広めにとり、1ページとして独立した印象に整える
このときよくあるミスが、改ページを入れずに本文の末尾に奥付を直接書いてしまうことです。
これをやると、端末によっては本文と奥付が混在してしまい、体裁が崩れる原因になります。
必ず改ページを使って「1ページとして区切る」というのが大事なポイントです。
また、文字のデザインを過剰に凝る必要はありません。
シンプルなレイアウトのほうが読みやすく、全体の完成度も上がります。
画像として挿入する場合の注意点
奥付画像を作る際のサイズ設定は『Kindle出版の表紙サイズとは?初心者でも失敗しない最適設定を徹底解説』を参考にすると安心です。
奥付をデザインツールなどで作成し、画像として挿入する方法もあります。
この方法は、商業書籍風の見た目にしたい場合や、特定のフォントやロゴを使いたいときに便利です。
ただし、いくつか注意点があります。
まず、画像サイズは端末によって表示が変わるため、解像度は十分に確保しておきましょう。
推奨は幅1000px程度以上で、縦横比は一般的なページ比率(A4に近い縦長)が無難です。
解像度が低いと、スマホやタブレットで拡大表示された際に文字がぼやけて読みにくくなります。
次に、画像にすべての情報を埋め込むと検索・コピーができません。
著作権表記はテキストでも併記し、可能なら代替テキストも設定しましょう(読者の可読性にも有利)。
KDPの内部検索では画像内の文字は認識されないため、権利情報や発行日を画像にしただけだと、検索や引用の観点で不便が生じることがあります。
そのため、実務的には「奥付デザインの画像+最低限のテキスト(著作権表記)」を併用する形式が安心です。
見た目と実用性の両方をバランスよく保つことができます。
最後に、画像はPDF化する前に必ずプレビューで表示を確認しましょう。
端末によって余白の取り方や改ページの位置がずれることがあるため、複数の端末でチェックするのがおすすめです。
奥付画像を作る際のサイズや比率の目安は『Kindle出版の表紙サイズとは?初心者でも失敗しない最適設定を徹底解説』が参考になります。
初心者がつまずきやすい奥付の注意点とよくある誤解
奥付はシンプルな構成で十分なのですが、初めてKindle出版をする人ほど細部でつまずきやすい部分でもあります。
実際、私も初回の出版時に「紙の本の奥付をそのまま真似したら見た目がゴチャゴチャになった」「奥付がないとKDPでエラーになると思い込んでいた」といった経験があります。
ここでは、初心者が特に勘違いやすい3つのポイントを整理しておきましょう。
紙の奥付と混同して、不要な情報を入れすぎる
もっとも多い失敗が、紙の奥付をそのまま電子書籍に当てはめてしまうケースです。
紙の本では、出版社名や印刷所、ISBN、定価、住所など、かなり細かい情報を掲載するのが一般的です。
しかし、Kindle電子書籍ではその多くが不要です。
KDP(Kindle ダイレクト・パブリッシング)では出版社や印刷所といった概念がないため、住所や電話番号などを載せる必要はまったくありません。
むしろ、住所などの個人情報をうっかり掲載してしまい、後から慌てて修正する著者も少なくありません。
私の周囲でも、個人出版で住所をそのまま入れてしまい、知らない人から手紙が届いたというケースが実際にありました。
電子書籍の奥付は「シンプル・最小限」が鉄則です。
著作権表記・著者名・発行日、この3点だけを丁寧に記載すれば十分です。
電子(Kindle本)ではISBNは不要です。
紙版を出す場合は要件が異なるため、ペーパーバックのガイドを参照してください(公式要確認)。
紙と電子の制度の違いを理解しておくことで、余計な情報を削ぎ落とせます。
奥付がないと出版できないと誤解してしまう
もう一つよくあるのが、「奥付を作らないとKDPで出版できない」と思い込むケースです。
結論から言うと、奥付はKDPの必須要件ではなく、なくても出版できます。
公式ヘルプにも「著作権ページの作成は任意」と明記されています。
ただし、実務的には奥付を入れておいた方が、著者情報の整理や読者への信頼感の面でメリットが大きいのは前述の通りです。
そのため、奥付は「入れないといけないもの」ではなく「入れておいた方が安心・便利なもの」という位置づけで考えるとよいでしょう。
初期設定やテンプレート化してしまえば、毎回の出版時に迷うこともなくなります。
ペーパーバックの場合の奥付の扱い(補足)
最後に補足として、ペーパーバック(紙の本)をKDPで出版する場合について触れておきます。
紙の書籍では、奥付の役割や必要な情報が電子書籍よりも多くなります。
たとえば、ISBNの付与や印刷情報、発行者情報などが必要になるケースがあります。
ただし、KDPのペーパーバック機能を使う場合でも、日本の商業出版と同じレベルの詳細な奥付を作る必要はありません。
基本的には電子書籍と同様、著作権・著者名・発行日を記載し、追加でISBNや印刷に関する情報を補足する程度で十分です。
詳しくはKDP公式ヘルプの「ペーパーバックの出版ガイドライン」を確認しておくと安心です。
ペーパーバックでは奥付の位置がレイアウトに直結するため、本文の最後の1ページにきれいに収まるよう調整しましょう。
電子書籍と紙では扱いが微妙に異なるため、両方を出版する場合は別々に管理するのが実務的です。
事例:実際のKindle本の奥付テンプレート例
ここまで解説してきたように、Kindleの奥付は法律で厳密な形式が決まっているわけではありません。
とはいえ、初めて作ると「具体的にどんなレイアウトにすればいいのか」がイメージしづらい方も多いと思います。
そこで、ここでは私自身や多くの著者が実際に使用している、シンプルな基本形と少し丁寧に作りたい方向けの応用形の2パターンをご紹介します。
どちらもKDPの仕様に準拠しており、初心者でもすぐに真似できる内容です。
奥付以外のテンプレートもまとめて確認したい方は『Kindle出版テンプレートの選び方と使い方を徹底解説|初心者が失敗しないポイントとは』をご覧ください。
シンプルな基本形の例
まずは、個人で出版する著者がもっともよく採用している最小限の基本形です。
この形式は、著作権表記・著者名・発行日の3項目だけを記載する非常にシンプルなものです。
―――
©{西暦} {著者名}
著者:{著者名 or ペンネーム}
発行日:{YYYY年M月D日}
―――
このように、1ページの中央に3行を配置するだけで成立します。
特別なデザインや装飾は不要で、フォントサイズを本文と合わせるか、やや小さめに整えると全体の印象が引き締まります。
「迷ったらまずこの形」と覚えておくと、毎回の出版作業が格段にスムーズになります。
私自身も最初の数冊はこの基本形を使っていました。
短時間で作成でき、審査にももちろん問題はありませんでした。
特に個人での出版やジャンルを問わず幅広く使える汎用性の高いテンプレートです。
少し丁寧にした応用例(企業・団体名を含む)
次に紹介するのは、企業名や団体名を加えて、少し正式な印象に仕上げる応用形です。
著者名と発行者名を分けたり、団体で制作した書籍や商業的な用途に使うときに向いています。
―――
©2025 株式会社〜〜〜〜
著者:石黒秀樹
発行者:株式会社〜〜〜〜
発行日:2025年10月11日
―――
このように、発行者欄を加えるだけでグッと書籍らしい印象になります。
企業としてブランドを明確にしたい場合や、複数人で制作した作品ではこの形式がおすすめです。
また、海外向けにも販売する場合は、著作権表記の下に英語の一行を追加することで国際的な体裁を整えることができます。
たとえば以下のようにします。
―――
Copyright © 2025 〜〜〜〜 Co., Ltd.
―――
必須ではありませんが、海外の読者にもわかりやすい権利表記を追加しておくと安心です。
この応用形はやや手間がかかる分、ブランドとしての見栄えや信頼感が増すため、ビジネス書や団体発行の書籍によく使われています。
私も法人名義で出版したときは、この形式をテンプレート化して使い回していました。
一度作っておくと、以降の出版で何度も使えるので非常に便利です。
まとめ|Kindle出版の奥付は「任意+基本3項目」で十分
Kindle出版における奥付は、KDPの公式ルール上は必須ではありません。
しかし、著作権・著者名・発行日という基本3項目を巻末に記載するだけで、本の信頼性や権利保護の面で大きなメリットがあります。
紙の本のように複雑な情報を入れる必要はなく、むしろシンプルなほうが読みやすく、実務的にも管理がしやすいです。
テンプレートを一度作っておけば、次回以降の出版作業でも迷わずにすみます。
奥付は本の目立つ部分ではありませんが、著者としての姿勢や丁寧さが表れる箇所でもあります。
自分の出版スタイルに合わせて、基本形・応用形のいずれかをベースに活用していきましょう。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。